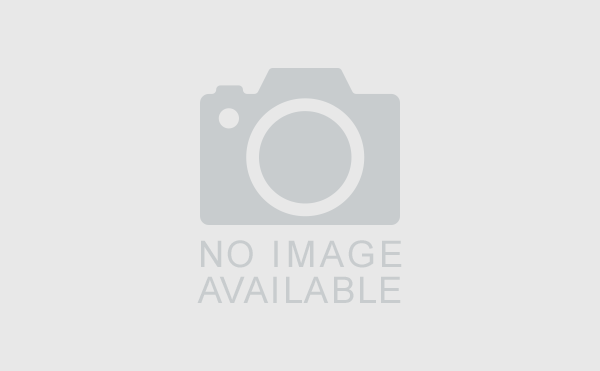読むだけで世界が変わる!天才科学者の思考法『天才科学者はこう考える』- いんすぴ!ゼミで学ぶ科学者の思考法
冒頭の言葉
読む? あとがき違うんじゃう? まぁでも読んだ方がいいな。ちょっと読んじゃうね、あとがき。
読むとものの見方、考え方、つまり世界観が変わる。
なかなかそういう本を書くのは難しいですね。面白い本。そうだね、私も常々思います。
事実の列挙と読者の求めるもの
やっぱりついね、本を書くっていうと辞書を書いちゃいたくなるんですよね。事実を正しく伝えることが大事だなと思っていて、事実を列挙したような本を書いちゃうわけです。でも、読者が知りたいのはそこじゃないんだろうなとも思うんですよね。結局、ここにも書いてあった通り、その人がどういう風に世界を見ているかっていう、その価値観が知りたい。そこに価値があるわけだよね。みんな一人一人が見ている世界って違って、世界の見方ってのは違うから、それが面白いんで。特に科学者ともなれば全然違う見方で見ている、それが見たい。それを知りたい。それはアートを鑑賞するようなものですね。その人の脳の中で作っている脳内モデルが見たい。世界の模型が見たいってことだよね。
“面白い本”を書くということ
っていう意味では、だから、誰もがそういう面白い本を書けるはず。だから、私はこういうふうに世界を見ているんだっていうことを、もしうまく言語化できれば、それはそれで非常に立派な面白い本ですよ。なるほど、こういう見方もあるんだっていうことになりますからね。見方が変われば、なるほどで終わらなくて、そうか、自分もそういう見方をしてみようとかってことになると、これまでなかった新たな世界の見方っていうのが生まれてくるわけですね。そうやって、だからそれを私は知恵ブクロ記憶って言ってますけど、より解像度が高くて豊かな知恵ブクロを作っていくことになるわけですね。確かに実用書が求められがちですが、確かにね。読むだけでいいんだよっていう本がね、確かに重要ですね。知恵ブクロ記憶ってのは言語化できる部分もありますけど、言語化できない部分もありますから、これはここが、だから面白い作業ですね。
言語化とコペルニクス的転回
自分と向き合うっていうのは、今まで言語化されていなかったものを言語化していくということになります。それはなかなか面白いですね。コペルニクス的転回っていうのがありますよね。発想を逆転させるっていうか、今思っている当たり前を崩していくってことですね。バイアスを取り除いていくということです。それが未来の当たり前を作っていくってことになりますね。私は昔から天邪鬼だったので、そういうのはちょっと得意ですね。発想を逆転して逆から見ていくみたいなね。まあ、ちょっとダラダラ喋ることもできますが。
読む本の背景
今日はですね、この「天才科学者はこう考える」という本を読むにあたって、この本がどういう経緯で作られたのかという「はじめに」の部分と、それから翻訳者がね、この本は間違いなく面白い本だと。面白いとは? ということで、世界の見方を変えてくれるんだ、ということですね。ということでした。そもそもこの本を読むみなさんが、この本を読むにあたって持っておく疑問っていうのが、「人々の認知能力を向上させ得る科学的な概念とは何か」ということを考えながら、念頭に置きながら読むと。これは私は文系だから関係ない、とかっていうことではなくて、科学者とは書いてますが、ここに出てくるのは必ずしも科学者ではないですね。そもそも科学っていうのはどういうことかっていうことです。その世界を分析するっていう意味においては、経済学だろうが政治だろうが文学だろうが、すべて科学ですよねっていうことです。なので、うん、まあ、確かにちょっとタイトルで損したかもしれない。理系の本ではないですよね、ということですね。むしろ哲学書とかに近いかもしれませんね。なんつったって、我々博士ですけれども、Ph.D.ですから。フィロソフィーですから。ドクターオブフィロソフィーですから哲学ですから。自然科学も哲学の一つに過ぎませんからね。