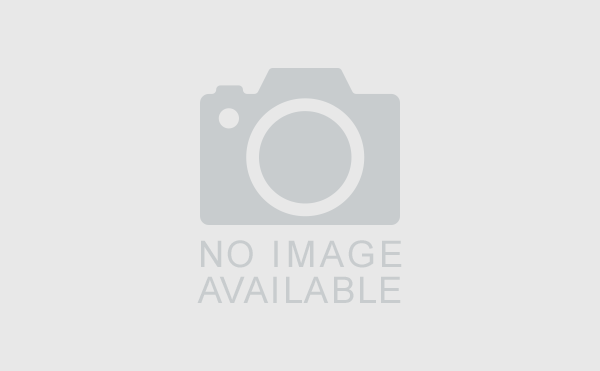できる人はみんなやってる「良い問いを立てる」質問力の鍛え方を一流科学者たちに学ぶ『天才科学者はこう考える』- いんすぴ!ゼミで学ぶ科学者の思考法
生き方と世界の見方
いいですね。なかなか生き方を真似するっていう、真似したいなと思える人、あるいは思ってもらえるっていいですね。私、松田聖子の古い古い歌で「赤いスイートピー」が好きで、歌詞でさ、「あなたの生き方が好き」っていうあれ、好きっていう、そうだね。「生き方が好き」っていう歌詞があって、さすが、すごい歌詞だなって。言われてみてえもんだってもんですよ。生き方が好きなんてね。ね、言われてみたいですね。ということです。だから生き方っていうか世界の見方ということですね。世界をどうやって見ているか。中には悲観的な人もいるでしょうということね。ポエムのように感じている人もいると。ただひとつ、これはみんな最先端を行く科学者が書いているというところがまた面白いですね。ここは人間だって人間的ですね。科学者とて人間的だということですね。
思考に役立つ道具を授ける本
これは思考に役立つ道具を授ける本だということですね。別に利益を生み出す、さっきも言ったように、ユースフルであるということだけではなくて、確かにユースフルな面もあるけど、世界の見方、切り取り方、そして人間とは何かということの解像度を上げてくれるっていうことだね。という本ですよ、ということでした。「はじめに」を今読みました。これはコラムニストがこの本を書評として書いた文章ですよね。なかなかうまいですね。やっぱり文章がね、ワクワクしますね。どんなことが書いてあるんだろうってね。
まえがきと編集者の存在
まえがき。これはジョン・ブロックマン。これ編集者が書いた文章ですね。こういう人がいることは大事ですね。なんかこう、私はこういうタイプじゃないんで、だけど中にはいますよね。もう会を開くことが好きな人。自分は何かそれこそ潤滑油じゃないけど、人が集まっているのを見てるのが好きみたいな。で、そういう場を提供してくれる人がいるっていうのはすごいですね。知的な思索をする会っていうのはいいですね。私も所属してます。麹町塾と呼んでいますが、所属っていうか主宰というか。これはいいですよ。何を生み出すでもなく、とにかく知的な楽しみを得るというかね。一応社会に役立つということで、経営者が脳科学を学ぶっていうのもひとつの柱になってますけども、今度秋に早稲田のMBAの授業になりますけれども、その取り組みがね、授業になっちゃうんだって感じですが、そうだ、それもやらなきゃいけないね。
Edgeの取り組みと思索中のアイデア
ということで、Edgeという会をこのジョン・ブロックマンは主宰している。これはオンラインなんだね。いろんな分野の最前線がわかる思索中のもの。いいですね。こういう思索中のものを、まだ発展途上の、発展途上のアイデアをどんどん出せる場所があるってのはいいですね。疑問を投げかける。問いを立てる能力っていうのは、問いを立てるってのは非常に難しいですね。いい問いが生まれれば、おのずといい答えが出てくるというか、いい問いが出てきたときにはワァってなりますね。これだ! という。
良い問いの重要性
私の例でいうと、私の例で恐縮だけど、脳が生きているとはどういうことか、生きているとはどういうことかとかね。脳を理解するだけで脳は理解できるのか? とかね。それから、本当に脳は必要? 脳など必要か? みたいな問いに今ぶち当たってますが、そういう問いを立てると次の研究の指針が決まってきます。そう、良い問いありきですね。良い問いを立てるってのがまず大事ですね。その次に仮説が立ってきます。そうするとその仮説を証明するための実験が生まれてきますから、まず問いが必要ですよね。これはでも小学生の時に習いましたよ。問いを立てようってね。SQ3R法っていう学習法がありまして、まず問いを立てながら本を読むんだっていうことです。ただ漫然と読書するのではなく、この本を読むことによって解きたい問いを置くということですね。
科学的概念と日常言語
科学から引用されて日常言語に溶け込み、幅広く適用できる。テンプレートと化して人々を知的にする言葉。知恵ブクロ記憶みたいなものでしょうかね。SHA(Shorthand Abstractions)と名付けた。規模が違いました。市場、プラセボ、無作為標本、自然主義的誤謬など。そうか、知恵ブクロ記憶は及ばないですね。
今年の問いの再掲
では早速今年の問いを次に紹介しよう。
「人々の認知能力を向上させ得る科学的な概念」は何か。
人々の認知能力を向上させ得る科学的な概念。なるほどね。
読書の方法とキーワード
この本に限らずですね、良い読書の方法としてSQ3Rというのが昔から言われていて、問いを立てるってのが大事ですね。問いを立てながら読むというのが大事で、次に大事なのはそれを自分の言葉で説明するってなってくるわけだけど、そうね。何か新しい言葉を発明すると、ふっと概念がまとまって、一つステップアップ、レベルアップするようなキーワードみたいなのがたまに生まれることがあります。僕も常々そういうのを考えていて、「科学から引用され、日常言語に溶け込む幅広く適用できるテンプレート」。これ大事ですね。だからもちろん科学的に厳密な言葉、概念ではあるんだけど、ちゃんと日常に溶け込むことができる、日常で使われる言葉であるということが大事ですね。造語しまくってもいいんだけど、造語だけだと意味わかんないですね。「手軽な抽象表現」というわけです。例えば、ということで、市場、プラセボ、無作為標本、自然主義的誤謬など。こういうのが発明されると、一気に議論の抽象度が上がって、人類はまた一歩レベルが上がるっていうですね。
本の構成と問いかけ
これを受けて、この本では、科学者たちに何を問うたかというと、「人々の認知能力を向上させ得る科学的な概念は何か」。難しいですね。人々の認知能力を向上させる科学的な概念は何かということを、151人に語ってもらったということですね。これはいいね。でも問いを変えれば、多分また別の答えが出てくるはず。だから、無限に本を書けますね。科学というのはかなり広い概念ですね、これ自体がね。別にフラスコを振ることだけが科学ではないですからね。人間の言動、企業の振る舞い、地球の宇宙の未来など、多岐に渡るはず。哲学、論理学、経済学、法律学など、何かを分析する活動から生まれてもおかしくない。ということで、別に文理の壁を越えて、科学的な概念で、しかもそれが人々の認知能力を向上させる。
認知能力を向上させるとは
認知能力を向上するってどういうことですか? 今まで見えなかったものが見えるとか、今まで分からなかったことが分かるということですよね。そうだから、どうやって世界を切り取れば、より解像度が高く、世界を認識、世界や自分のことを認識できるのかということですね。
次回予告
「はじめに」を読んできまして、次回から実際に読んでいきます。まあどうしようかな。本当に151人いるので、例えば短くね、短くてもいいと思うんですよね、最近動画ね。だから1項読むごとに切って、「はい、こんにちは、いんすぴ!ゼミです」って始まって、また始まって、また終わってみたいのを7回やって1セット。そうだな、もう10、10分もやったら、10分やったらちょうど1時間いかないぐらいかな。10分、5分で読んで5分解説するみたいな解説というか、ああだこうだ言うという感じですかね。そうすると、7個、一回につき7回7個取れるので、5分以下の短い動画にして、皆さんに公開するという感じかな。理想的には、あるいは「はい、こんにちは」というところはカットしてもいいかもしれませんね。最近は便利なAIのアバターがいるので、その人にしゃべってもらうっていうのもありですね、導入部分をね。
目次を見てみる
というわけで、ちょっと目次を見てみるとですね、本当に脈絡もないですね。すごいね。意図的でしょうね。章に分けてないです。例えば宇宙編とか脳科学編とか経済編とかって分けてやるかと思いきや、全く分けられてなくて、突然まず宇宙の話が2連続きて、でも割と、そうでもないか。脈絡がないですね。なんでこの順番にしたのかっていうのは、あとがきとかに書いてあるのかな。あとがきも読みたかったね。じゃあ次回はあとがきを読みましょう。
翻訳者への感謝
冒頭に言いましたが、翻訳者ってのは本当に素晴らしい職業です。この本を翻訳したのは夏目大という方と、花塚恵さんという方ですね。夏目大さん、どういう役割分担でやったのかわからないけど、いや本当にね、本当に翻訳者っていうのは素晴らしい職業。それ私それに尽きるね。翻訳。この日本語で美しい日本語で読めるっていうのが感謝しかないです。ただ、エモーションは感情と訳さないでくださいというお願いだけですね。